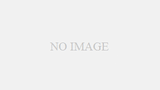臨床検査について
臨床検査という言葉を聞いたことがあっても、どのような検査なのか詳しく知らない場合もあります。
尿や血液を検査してもらった経験は誰にでもあるでしょう。
臨床検査とは、おおまかに表現するとその馴染み深い検査のことです。
その他にも心電図を用いた検査なども該当するように、とても幅広いことが特徴といえます。
このような検査において、尿や血液をとることは医療行為にあたるため、基本的には病院などの医療施設でしか実施できません。
ただし、その後の作業についてはルールが守られる限り、医療施設でなくても実施することが認められています。
このような事情があるので、実際には医療施設以外の施設に作業を部分的に任せているケースも多いです。
それでは、この仕事をする職業に就くにはどうしたら良いのでしょうか。
まず前提として臨床検査技師という国家資格を取得しなければなりません。
高等学校を卒業した後に、臨床検査の教育を受けられる大学などで学ぶ必要があります。
定められているカリキュラムを修了した人が、国家試験を受けて合格することで取得できます。
国家試験の難易度は極端に高いわけではないので、しっかり対策をしていれば合格できる可能性が高いです。
就職後も勉強を続けていくことが大事
しかし、受験のための勉強をするだけで満足してはいけません。
受験対策をしているときだけでなく、就職後も勉強を続けていくことが大事です。
なぜなら検査の技術は日々進化を続けているからです。
そのような技術を身に付けていないと、おのずと仕事の幅は狭まっていくことになります。
古い技術は新しい技術に置き換えられていくので、自分ひとりで対応できる仕事が減っていくことになるでしょう。
また機械の発達により、自動で行われる検査が増えていることも意識しなければなりません。
つまり人手が不要になっている項目が増加しており、これからも増え続けていくと予想されます。
一般的に古い簡単な項目から自動化は進んでいくので、そのような観点でも新しい技術を身に付けることは重要といえます。
こういった背景があるため、これまでの検査にこだわらずに製薬の企業で働いたりするなど、職場が多様化している傾向が見受けられます。
第一線で必要とされる付加価値をつけていくことが重要
これから高齢者が多くなっていくのは明らかなので、検査を必要とする人の割合も高くなっていくと考えられます。
すなわちニーズ自体は減るわけではないので、第一線で必要とされる付加価値をつけていくことが重要です。
付加価値を付けるには、前述のように常に勉強する姿勢を持たなければなりません。
医療関係の仕事をする人なら誰にでも言えることですが、向上心がなければ医療環境の変化に付いていくことは難しいです。
そのため施設内で勉強会やセミナーを実施しているケースも多く見受けられます。
ただでさえ医療の仕事は忙しいのに、そのような余裕はないと嘆きたくなる場合もあるでしょう。
しかし業務が終わった後や定休日などをうまく使って、効率よく取り組んでいくことが大切です。
学生時代にあまり勉強する習慣がなかった人は、プライベートの時間が減ることに抵抗感を覚えるかもしれません。
しかし臨床検査の仕事を続けていくには、このような心構えでは通用しない恐れがあります。
仕事内容にあまり興味が持てなかったとしても、努力を続けていく決意を持って臨むことが望まれます。
細かいことに気が付く性格の方が活躍しやすい
デスクワークをはじめとした一般的な仕事とは異なるため、向上心以外にも持ち合わせている方が良い素養が多くあります。
たとえば大雑把な性格ではなくて、細かいことに気が付く性格の方が活躍しやすいです。
いろいろな精密機器を操作することになり、さまざまな物を少量ずつ扱う機会が日常的にあります。
血液の標本をつくるような作業は、ミスがないように注意深く行わなければなりません。
そのため性格的に細かいだけでなく、器用な手先を持っている人にも適しています。
このように丁寧に仕事をする性格と、精密な作業をする器用さがある人だと向いている可能性が高いです。
ただし、それだけでは不十分である可能性もあります。
どれだけ向いていても、いい加減な気持ちで仕事をすると人命に関わるケースがあるからです。
検査で見落としがあると、重大な病気に気付かずに放置することになるかもしれません。
検査を受けてる患者とのコミュニケーションも重要な仕事のひとつ
自分の働きが患者の人生を左右しかねないことを認識することが肝心です。
そのうえで強い責任感を持って、いつも気を抜かずに注意を払って仕事をする必要があります。
ただし、集中して作業を続けるだけで良いわけではありません。
検査を受けてる患者とのコミュニケーションも重要な仕事のひとつです。
担当によっては患者と話す機会がないケースもありますが、職場のスタッフと情報交換をする機会はあります。
抜かりなく情報を伝え合わないと、大きなミスにつながることもあるので要注意です。
口下手の自覚があるなら、せめて正確に伝えられるように事前にメモしておくなどの工夫をすると良いでしょう。
出典元
最終更新日 2026年1月28日 by トゥルソワソワ